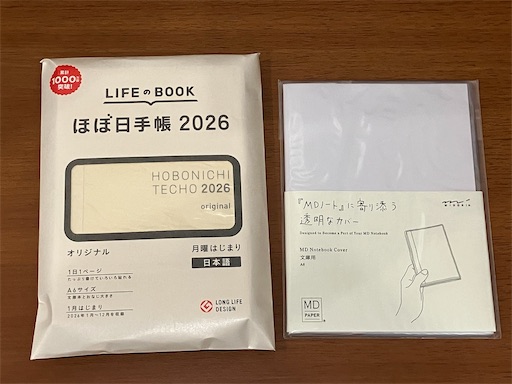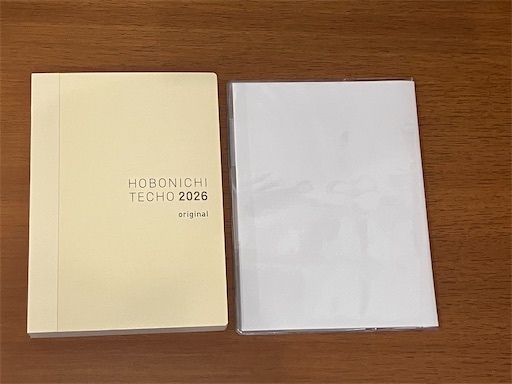太平洋戦争末期のペリリュー島の戦いを描いた原作の映画化。可愛い絵柄とは裏腹に戦場での悲惨さは十分に描かれていますが、後半は島で潜伏するサバイバルものになるので、派手な戦場での戦いや悲劇という意味では少し物足りなく感じるかもしれません。
ただ、水木しげるの『総員玉砕せよ!』などでも度々登場しますが、全ての兵隊が華々しく死んでいったわけでない、その残酷さが現れているとも言えます。スコールの後に脚を滑らせて頭をぶつけて死んだり、水を調達しに水場に来たところを狙い撃たれて死んだり、関係ないところでワニに喰われて死んだり(これは『総員玉砕せよ!』ですが)など、しょうもないことで人がポコポコ死んでいく。昨日まで笑い合っていた仲間が「出征する時にはこんな酷い死に方をするなんて思わなかっただろう」死に方をしていく。主人公の田丸は部隊の功績係として死んだ者の最期を伝える役割を与えられるのですが、最初に「脚を滑らせて死んだ」兵隊の最期を盛って盛って勇ましく戦死したことにする。こんなことが当時もあったんだろうなと思うと辛く悲しくなります。こんなことをして何になるんだ、と。
しかし、この映画が描こうとしているのは、そうした戦場の「虚飾」とは異なる「創作」の力強さではないかと思います。映画では描かれていない原作では戦後、生き残った片倉兵長がペリリューの話を描こうとする後村 亮(主人公、田村の孫)たちに「話を聞けば体験していなくても描けるとお考えですか?」と突き放すシーンがあります。ペリリューの地獄を味わっていない、戦争を体験していない人が「あれ」を描くことなんてできない、描く資格なんてない、という理屈は確かに理解できます。簡単に自分たちを物語として消費するんじゃない、されてたまるかという思いはそれ自体として尊重されるべきでしょう。当事者でなければわからない思いは確かに存在するはずです。
しかし、それでもこのペリリューの戦いが漫画化され、映画化された意味は確かにあるはずです。勇ましいだけではない戦争の悲惨さ、追い詰められた人間の残虐性、それらを物語として残すことができなければ、創作の意味など儚いものなのでしょう。その意味でペリリューの戦いを描いてくれたこと、そして映画化に向けて長大な原作をうまくまとめてくれた映画版スタッフに感謝しつつ、そして戦場とはとりあえず無縁の日常を噛み締めつつ鑑賞すべき作品と思えます。

![ほぼ日手帳2026本体オリジナル[A6/1日1ページ/1月/月曜はじまり] ほぼ日手帳2026本体オリジナル[A6/1日1ページ/1月/月曜はじまり]](https://m.media-amazon.com/images/I/21a3pdJlMcL._SL500_.jpg)